
問題に悩む
業務アプリ開発 はじまりから運用までの16ステップ~ indexはこちら
アプリというと、BtoC、つまり一般ユーザが利用するゲームやSNSなどのアプリを想像するかもしれませんが、今回は、業務系アプリを開発する場合、かつ開発を外部委託する場合を前提として説明しています。
今回は、1番目のステップ「課題・問題点を洗い出す」です。
1.課題・問題を洗い出す
アプリを開発しなければならない。
そうなったからには、必ず理由があり、目的があるでしょう。
業務アプリであるからには、業務効率改善、業務管理、経営分析などが目的となります。
これらの目的が生まれる背景には、必ず課題・問題点があります。
例え上司から、「営業部門の業務効率が悪いから、効率を上げるためにシステム化を進めよ。いまはスマホ時代だから、スマホアプリを作ればいいんじゃないか」と言われたからと言って、すぐにアプリ開発業者へ連絡をして相見積するようなことはしないでください。
アプリ開発はよくわからないから教えてください。というご依頼はよく頂くものの、自身の知識がある程度ないと、悪い言い方をするならば業者の言いなりになる可能性も秘めるわけです。
アプリ開発そのものは分からないとしても、「自社の課題・問題は具体的にこうである。だから、アプリを導入することでこんな効果を期待している。この期待が正しいのか、あるいは別の解決策があるか、提案してほしい」と言うところまでは準備が必要です。
ところで課題と問題の違いは何だろう?
仕事をしていて、課題、問題と使うことがあります。問題だとネガティブな表現だから、課題と置き換えようと考えている方もいらっしゃるかと思います。(私が昔そうだったように。。。)
しかし、課題と問題は似て非なるものなのです。
「問題」とは、現状と理想の状態におけるギャップ
「課題」とは、問題となっているギャップを埋めるための事柄
前述の上司から言われた「営業部門の業務効率が悪いから、効率を上げるためにシステム化を進めよ。いまはスマホ時代だから、スマホアプリを作ればいいんじゃないか」
「業務効率が悪い」これは確かに問題のようです。
しかし、ここから課題を導くことができるでしょうか?
業務効率が悪いというのは、具体性に欠いています。
やるべきことは、営業の業務がどのように構成されているのかを知り、そのどの部分に理想とのギャップが生じているかを知ることです。
例えば、ある営業さんは、毎朝出社し、その日の訪問先を決定。訪問先へ渡す資料などを探し車に積み込み出発。一日が終わったら、帰社し業務報告書を作成して帰宅する。としましょう。
そして、できる営業担当は一日平均6件回れているのだが、多くは3件しか回れていない。営業効率が悪い!とした場合に、これを問題と考えます。
ただ、まだこれでは問題が大雑把すぎます。
業務フローを作って整理してみる
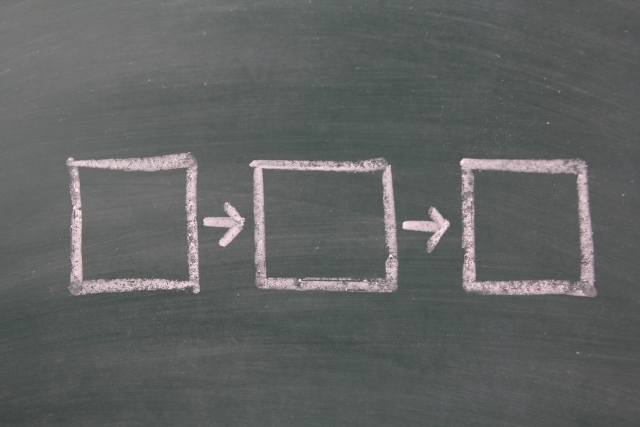
問題を具体化するにあたっては、改めて業務フローを作り整理するのが一番です。
既に、そのような資料があるならばそれをもとに進めるのもいいでしょう。
前述のケースの業務フローは以下の通りでした。
『出社』→『訪問先を決定』→『資料の用意』→『訪問』→『帰社』→『業務報告』
このそれぞれで、何が行われているのかを知る必要があります。
『出社』平均60分をかけて通勤している
『訪問先を決定』本人の感覚で、そろそろ訪問すべきところを決めている
『資料の用意』本人の感覚で、おススメ商品を決めて資料を用意する
『訪問』会社へ戻る際に楽になるように、遠いところから行くようにしている
『帰社』終わり次第戻る
『業務報告』業務報告書を書いて上司へ提出
(実際にこんな突っ込みどころ満載な会社があるかは別としてください)
このくらいのことが分かっただけでも、直感的に各担当者の感覚に依存しすぎるのはどうなんだろう?出社、帰社の時間は必要なのだろうか?という疑問が浮かんできます。
現場の話を徹底的に聞いてみる
業務フローができたなら(その前に、業務フローを作るためのヒアリングも必要かと思いますが)、数名の現場担当者、現場の責任者に話を聞いてみます。
そもそも、業務フローは正しいのか?
業務フローで、行われていることを具体的に
そこに問題があると感じているのか?あるならば、どうなるのが理想なのか?
そんな視点でヒアリングします。
そうすると、「直行・直帰でいいのではないか」、「訪問先を決めるにあたっては、3ケ月以上訪問していないところを優先しているのだが、それだけを基準にしてはいけない気がする」、「PCから入力している受注内容と重複することを業務報告書に記載しているが2度手間だと思う」などといった声が上がってくるかもしれません。
人によって、表現方法はバラバラでしょうから、類似する内容に分類して問題点を整理します。
問題の解決策を課題化する
例えば、ヒアリングの結果、訪問先の決定基準が曖昧であることが分かった。本来は、受注の確度を数値化し、確度が高いところを優先的に回るべき。という理想があるならば、課題として考えられるのは以下のようなものでしょう。
・受注確度を可視化するためのルールを定める。それは人によって異なるものとなってはいけない
・受注確度を記録する
・受注確度で、顧客を容易に選別できる
このように1つの問題に対して、複数の課題が上がってくるはずです。
課題に優先順位をつける
作業を進めていくことで、たくさんの課題が生まれてくることでしょう。
そもそも、その課題は達成が可能なものかどうかという判断もあります。
例えば、出社時間が無駄だから直行直帰にしたい。と言ったところで、会社の方針から変えなければならなくなるかもしれません。社長が、社員は家族。毎日顔を合わせることがコミュニケーションをよくするものだ。という強い信念があるならば、簡単にはいかないかもしれません。
達成の難易度も勘案しつつ、課題に優先順位をつけていきます。
優先順位は、その課題を解決することによって効果が大きいであろうものを上位にします。
ひととおり、順位付けができたなら、当初ヒアリングをした人たちと意見交換をし、最終的な順位付けを決定するとよいでしょう。
このような手順を踏んで課題・問題点を洗い出してみてください。
スマホアプリを使った業務システム構築のことなら
株式会社クラボードへお気軽にご相談ください
